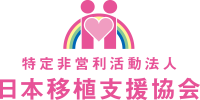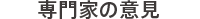|
聖マリアンナ医科大学 2010年 |
「死後臓器提供での医療機関が抱える諸問題」
本邦では1997年に臓器移植法が制定され、脳死下臓器提供が行われてきたが年間10件前後の提供数でありあまりにも少なかった。その後、臓器の移植に関する法律(臓器移植法)が改正され、国民の臓器移植に対する関心は非常に高くなった。また法改正後の脳死下臓器提供が増加しているように見えるが、現在でも臓器不全に苦しみ移植を待ち続ける命にとっては厳しい状況にある。そして2008年「イスタンブール宣言」では自国の臓器移植における自立性を提示されたが、いまだに医療者が自国の死後臓器提供の全体像を正確に判断すらできていないのが現状である。
それでは医療現場のどこで死後臓器提供が発生するのかといえば医療機関のなかでも多忙を極める救急医療の現場が中心となる。救急医療現場では医師、看護師をはじめ多くの専門スタッフがチームとして移植医療以外の通常業務に関わる。そんな中、法改正施行により小児臓器提供や虐待問題、親族優先など現場負担が増える要素は大きくなった。
通常業務でさえ多い中、発生時の周りに影響する負担は大きくなったことは事実である。また臓器提供を死後の事と認識している方々もいるが、実はそうではない。どのような経過であれ、入院され医療を開始した際には意思表示カード所持の確認、家族からの希望、そして医療スタッフからの選択肢提示により臓器提供に対する対応が始まっている。つまり臓器提供とは死亡から始まるのではなく、あくまでも本人の意志や家族の希望で臓器提供の対応が始まるため、入院後の治療経過中においても医療スタッフの対応が大切となる。
よって法改正後の臓器提供に対して公正・公平に関与するためには個人の対応を避け、まず脳死診断を含めた終末期医療に対する医療スタッフの理解向上と救急現場を支える院内体制整備が必要となる。脳死下もしくは心停止下臓器提供のいずれでも「人の死」を前提とし、死に行く者の臓器提供があり初めて臓器移植が行われる。これまでの臓器提供症例においては、一部の医師もしくは医療機関により支えられてきたことは事実である。実際、すべての脳神経外科医や救急医が積極的に臓器提供には関わっていない。
その一面には脳死診断や選択肢提示が終末期医療のなかでは日常業務以外と考えているからである。多くの場合、脳死もしくは全脳の機能不全を避けられない状況で医師は「脳死の診断」を行い、家族に十分な病状説明を行いその後の治療方針を問う。このような状況で医師を含めたスタッフは病気に対する敗北や無念さを感じているものの、その一方で終末期医療や臓器提供に多くのトラブルを抱え込むことを嫌う傾向が多い。もちろん医師の主な仕事は病気を治すことであるが、医師個人の苦悩は理解される一方で、医療スタッフは危機にある命のために最後まで治療を施す義務があり、出棺までも本人や家族のためにあらゆる努力を忘れてはならない。
つまり脳死状態、もしくは予後不良だからといって医療機関の努力をDNARといった言葉で一方的に終わりにすべきではない。法改正をふまえれば、誰であれ医療機関に属するスタッフは本人や家族の「終末期における意志のベクトル」を能動的に問い、その中で臓器提供の可能性を見出していく努力が必要になる。その中で見えてくる課題としては、本人や家族の臓器提供意思を確認するためには情報を抽出するための選択肢提示を誰がいつ、どのタイミングで行うのかが問題になる。多くの施設では選択肢提示を行うべきは主治医であるとしているが、多くの医師の苦悩はここを起点としている。前述のように特に救急現場で医師は患者を救うために医療を施しているのである。選択肢提示は死を意味することでもあり、「手のひらを返すよう」に簡単に提示できるものではない。また終末期における脳死診断をはじめ、気管内挿管行為や人口呼吸器使用方法、昇圧剤、点滴量とドナー管理との関係も判断できない医療現場すらある。
しかもこれらの諸問題は少なくとも日本臓器移植コーディネーターが解決する内容ではない。あくまでも医療機関やそこで働く医療スタッフが解決してかなければならない問題である。そこで我々の施設では移植医療支援室を2007年から院内設置し、臓器提供に対する終末期医療とコミュニケーションスキルを中心に救急現場への支援を継続している。今後もこのような院内サポート体制は各医療機関のオーダーメイドでよいと思われるが、臓器提供に対する意思は常時、抵抗なく表示でき、その意思に沿えるようにできる体制を築くことが我々の責務であろうと思う。(H23.7)